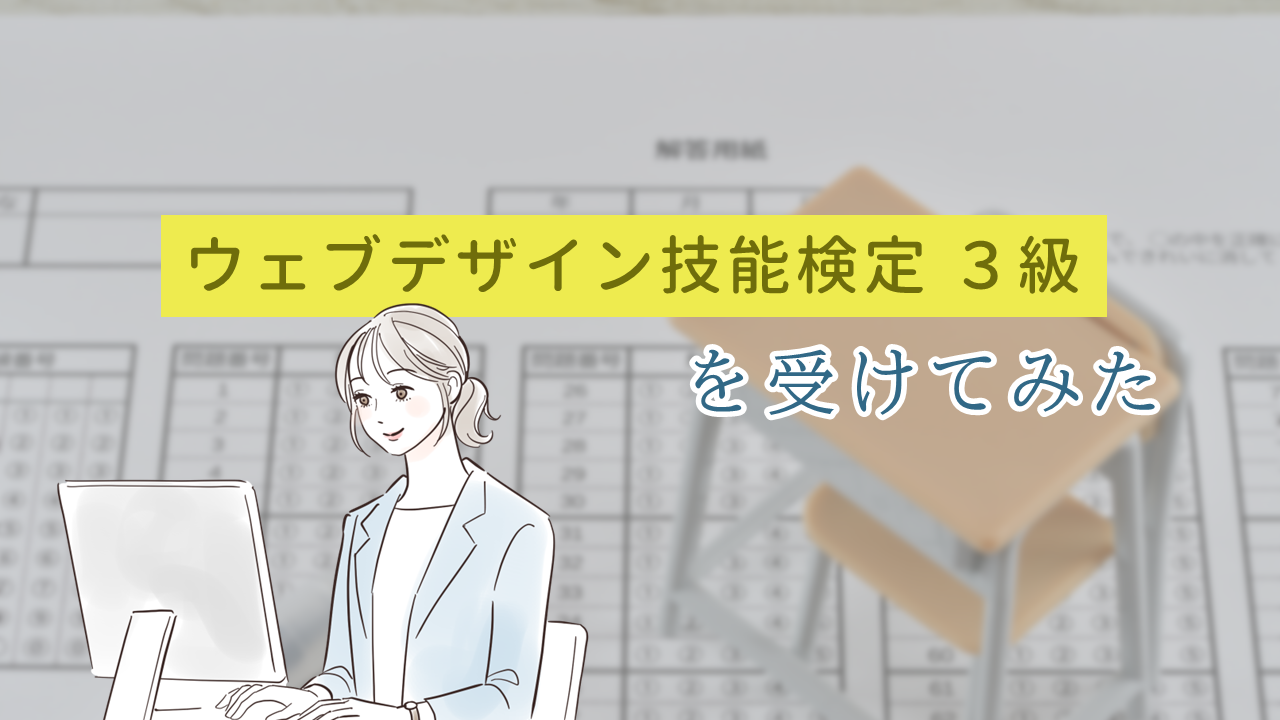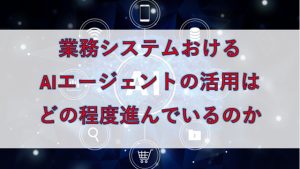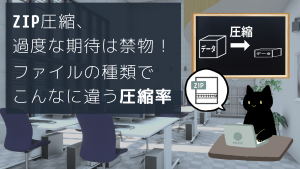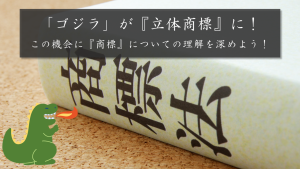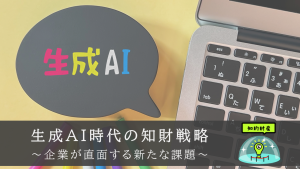はじめまして。
システム統括部、4年目のTです。
今回は、3年目の夏に受験した「ウェブデザイン技能検定3級」の経験談をご紹介します。
「ウェブデザイン技能検定3級」とは?
ウェブデザイン技能検定は、国家検定制度である技能検定制度の一つとして、厚生労働省より職業能力開発促進法第47条第1項の規定に基づき指定試験機関の指定を受け、特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会(以下、当協会)が実施するものです。
試験は実技および学科試験で実施され、関連国際標準規格等に基づき、ウェブデザインに関する知識・技能、実務能力等が問われます。
1級の合格者には厚生労働大臣より、2級及び3級の合格者には当協会理事長より、ウェブデザイン技能士の合格証書が発行されます。
引用元:ウェブデザイン技能検定公式HP
ウェブデザイン技能検定3級の試験は、「学科試験」と「実技試験」の2つで構成されています。
「学科試験」は、マークシート形式で25問ほど出題されます。
試験時間は45分です。
「実技試験」は、指示された内容に従ってHTMLやCSSを修正する形式で、全6課題のうち5課題を選んで回答します。
指定されたディレクトリ構造に沿ってファイルを整理したり、画像パスの修正やリンク設定の変更などが求められます。
試験時間は60分です。
学科・実技ともに、100点満点中70点以上が合格ラインです。
受験した理由
入社当初からフロントエンドやWebデザインに興味があり、また携わっていたプロジェクトでもWeb画面の作成をしていたので、それなら何か資格を取得してみようと思い、「Web 資格」と検索したところ、唯一の国家資格である「ウェブデザイン技能検定」があることを知り、挑戦することに決めました。
勉強方法/勉強時間/ポイント
学科
学科試験では、HTMLやCSSの文法だけでなく、色彩設計、著作権などの法律知識、ネットワークの基礎など、Web技術全般に関する幅広い知識が問われます。
私は、約1ヶ月かけて学習しました。
最初の1〜2週間は「改訂版 ウェブデザイン技能検定3級 過去問題集」を使って、テキスト中心に基礎知識を身につけました。
繰り返し問題を解くことで、出題傾向や紛らわしい選択肢、苦手分野が少しずつ見えてきました。
特に「インターネット概論(OSI参照モデル、TCP/IP、セキュリティ技術など)」の用語は初めて触れるものもあり、苦戦しました。
残りの期間は、公式サイトの練習問題や過去問題を活用し、より多くの問題に触れて試験形式に慣れることを意識しました。
実技
最初は、(公式ではありませんが)YouTubeにある実技試験対策動画を視聴し、試験形式や作業の流れを把握しました。
その後、参考書籍や公式サイトに掲載されている練習問題や過去問題を使って、実際に手を動かしてコーディングを行いました。
時間を計って練習することで、本番の時間感覚を掴むことができました。
<参考書籍>
<公式サイト 過去問題>
試験当日
学科試験は、過去問の時よりも難しく感じ、試験時間ギリギリまで悩みました。
問題用紙は持ち帰ることができたので、回答をメモして自己採点を行いました。
実技試験は、過去問とほぼ同じ内容で、スムーズに取り組むことができました。
試験勉強の際、実際に手を動かして練習していたことで、落ち着いて試験に臨むことができました。
反省点/気付き、お伝えしたいこと
学科は“ちゃんと”勉強した方がいい!と思います。
私は練習問題や過去問を繰り返すうちに、問題そのものを覚えてしまっていました。
そのため、本番で形式や表現が異なる問題が出題されたときに、「なんとなく知っている」程度の理解だったようで、少し戸惑ってしまいました。
問題に慣れるだけでなく、用語や仕組みをしっかり理解することが大切だと思いました。
実技は問題の傾向として、相対パスの理解や簡単なHTML・CSSが書ければ、そこまで難易度は高くないと感じました。
落ち着いて問題文をよく読み、冷静に取り組めば十分に対応できる内容だと思います。