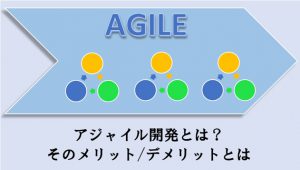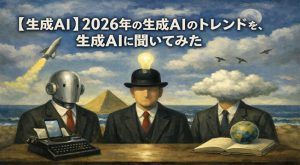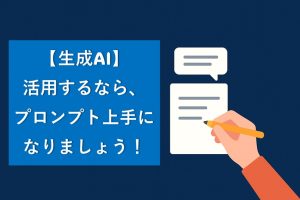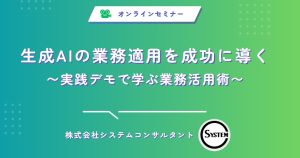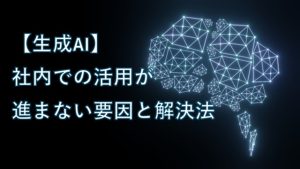大学入学共通テストの科目に「情報関係基礎」がある
1月15、16の両日、大学入試センターの共通テストが行われました。
https://www.dnc.ac.jp/
高校3年生の娘を持つ50代の営業部社員が、当社勤続30ウン年の経験をフル活用して、共通テストの教科「数学②」の別冊となっている科目「情報関係基礎」を解いてみようじゃないか、という無謀な挑戦をしてみました。果たして何点取れるのか!?そして娘に自慢できるのか!?
久しぶりの試験のつもりで・・・

某日12:50、事前に印刷した「情報関係基礎」の問題を、いつもの在宅勤務の作業場所に置く。枚数が多い。20ページ以上ある。それだけ問題数も多いということか。不安がよぎるのは否めない。
問題は大問が4つ。第1問と第2問は回答必須、第3問と第4問はどちらかを選択して回答だ。
高校生と同じように60分で解くことを前提に、13:00いよいよスタート!
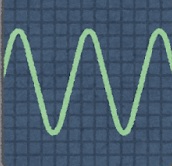
ページをめくり第1問を見る。ピクトグラムの例や2次元コードがある。問題を読む。細かな問題がいくつも出されている。画像データのビット数計算や著作者の権利、アナログ信号のデジタル化など広い知識が求められる問題だ。
業務アプリケーションの開発と営業の経験だけでは知らないことが多い。勉強不足を実感。習うは一生だ。
迷いながらもえいや、で第1問を回答し、次の大問へ。

第2問。回文?幸いさ?読解力が必要そうな問題だ。「しんぶんし」「たけやぶやけた」余計な回文が頭をよぎる。ダメだダメだ、集中しなくては。おっと、「ダメだダメだ」も回文だ。回文の分解。これは回文じゃないな。
1文字でも回文とみなす点だけ注意すれば、比較的分かりやすい。後半の問題には表も書かれている。その表を使って、何とか答えを選択する。表を繕うとはこのことか。
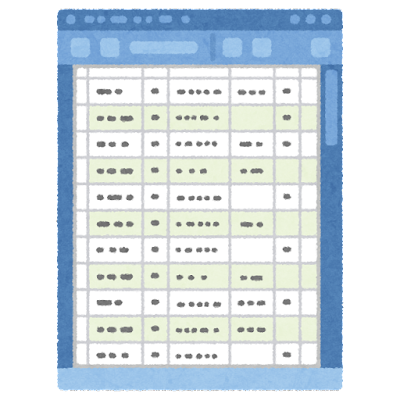
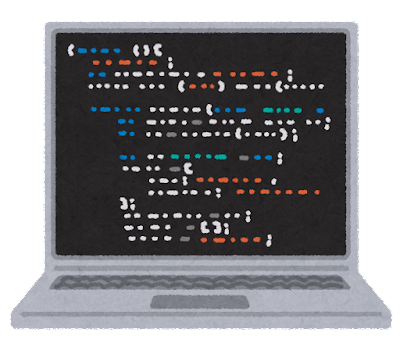
よし、これで必須問題は終わりだ。選択問題はどちらを選択しようか。
第3問と第4問を見る。第3問はあみだくじのロジック構築問題で、第4問はExcelっぽい表計算問題か。最近はExcelを使うことが多いが、ここはひとつ昔取った篠塚で、いや杵柄で、第3問を選択だ!

あみだくじなら何とかなるだろう、という甘い考えはすぐに叩き潰された。関数と変数、引数が混乱してきた。マズい。穴埋めの選択肢を見る前に、1ステップごとにロジックを書こう。仕様書のように。
しかし、自分のロジックと設問のステップ数が違っている。COBOLの頭ではどうしてもステップ数が増えてしまう。しかし時間がない。このままいくか。
あみだくじのスタートとゴールの駒の配置が分かっているので、逆にたどっていけばあみだ1行ごとの配置は当てられそうだ。千里の道も一歩から。

こうして、なんとか第3問まで終了した。時間を見る。14:02。制限時間をちょっと過ぎてしまったが、年齢に免じて許してやってください。
自己採点をする前に、せっかくなので第4問も解くことにする。

第4問はExcelのような表計算ソフトで対戦結果を集計するという問題。会社の野球チームの個人成績をExcelでまとめていたこともあるので、こっちにすれば良かったかも。後悔先に立たず。ブログ公開も先にできず。
コピペの問題。オートフィル的な使い方かな。関数の選択問題もある。わざと計算を難しくしてる気もするが、それが試験というものだろう。
第4問も終了した。どうにかこうにか情報関係基礎を解くことができた。何点取れているかは甚だ不安だが。
自己採点は、コーヒーブレイク後としよう。そういえば、今年の情報関係基礎の試験日は正月の十六日。地獄の釜の蓋が開く日だ。適度な休息は必要です。


自己採点。
第1問。アナログ信号のデジタル化のところが全然ダメだ。配点30点中19点。
第2問。回文は好調、全問正解だ。配点35点中35点。
第3問。あみだくじのロジック構築。やはり関数と変数、引数の混乱が不正解を招いた。配点35点中22点。

ということで、私の得点は76点、となりました。まあ、こんなもんでしょうか。
ついでに第4問も採点。プログラムのロジック構築よりもExcelの方が慣れていることもあり、比較的順調に正解しているぞ。配点35点中28点。こちらを選択していれば、82点だったのか。取捨選択は重要です。
解答を終えて
令和4年2月7日付で令和4年度大学入学共通テスト実施結果の概要が公表され、今年度の「情報関係基礎」は受験者数362名、平均57.61点と発表されています。
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r4.html
「情報関係基礎」という試験項目は、「数学②」という科目として、大学入試センター試験のころの平成9年(1997年)から実施されてきたそうです。
今年度からは全国全ての高校生が同じ内容を学ぶ「情報Ⅰ」の履修が開始され、令和7年(2025年)からは大学入学共通テストの科目にも「情報」が追加されることも発表されています。
子どものころからスマートフォンやパソコンが身近にある「デジタルネイティブ」世代にとって、インターネットを情報収集や情報発信の手段として使うことは、普通のことのように見受けられます。それだけに、アーキテクチャやセキュリティリスクなど、基本的な情報教育を若いうちから行うことはとても重要だと思います。
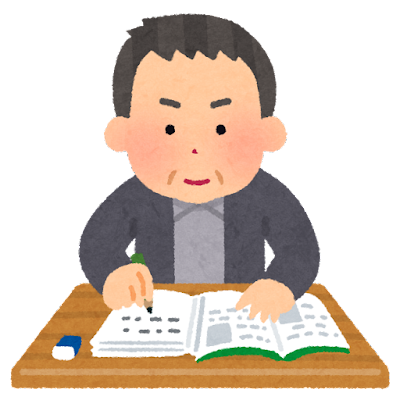
また、情報技術は日進月歩、分進秒歩などとも表現されるくらい、常に新しい技術が生み出されています。常日頃からの情報収集、勉強の継続が必要であることを実感した日となりました。
継続は力なり!
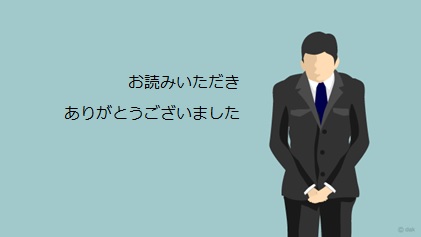
最後までお読みいただき、ありがとうございました。